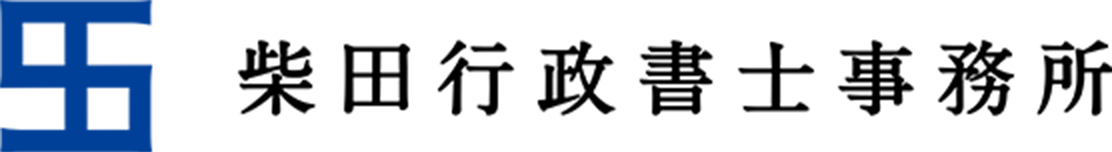相続税が払えない ときはどうする?対処法について解説
財産を相続した際に発生する税金である相続税。
場合によっては数千万円、数億円の納税額になることもありますが、
相続税が払えない ときはどうすればよいのでしょうか?
まずは、そもそも財産を受け取っているにも関わらずどうして 相続税が払えない ケースがあるのかについて確認していきましょう。
目次
相続税が払えない 主な原因
相続財産の大半が不動産であるため 相続税が払えない ケース
相続税は原則として現金での一括納付が必要です。そのため、相続財産の中で不動産の占める割合が高いと、手持ちの現金が不足し、納税が困難になるケースがあります。
相続不動産の売却が難航し 相続税が払えない ケース
相続不動産を売却して相続税を支払おうとする場合でも、売却には時間がかかることがあります。特に相続税の申告と納税期限である10カ月以内に売却を完了できない場合、資金調達が間に合わなくなる可能性があります。さらに、買い手が見つからない場合や希望条件での売却ができない場合も問題となります。
相続税が支払えない 場合の影響とは?
期限内に 相続税が支払えない 場合のリスク
相続税の支払いが期限内にできないと、ペナルティが課される可能性があります。このペナルティには無申告加算税や延滞税が含まれ、納税が遅れるほど金銭的な負担が大きくなります。
無申告加算税とは
正当な理由なく申告や納税が期限内に行われなかった場合に課税されるのが無申告加算税です。税務調査の事前通知前に自主的に申告した場合は税額の5%、通知後に申告した場合は10%〜20%の加算税が適用されます。
延滞税とは
相続税の納付期限を過ぎた場合に課される延滞税は、利息に相当する金額として発生します。期限後2か月間は2.5%、それ以降は8.8%(令和3年時点)と段階的に増加します。
財産の差し押さえや競売のリスク
相続税が長期間支払われない場合、国税庁による財産の差し押さえが行われる可能性があります。不動産が主な対象ですが、場合によっては動産も差し押さえられ、競売にかけられることもあります。
連帯納付義務がもたらす影響
相続税の滞納は他の相続人にも影響を及ぼします。同じ被相続人から遺産を相続した他の相続人に対し、連帯納付義務が発生するためです。これにより、滞納者以外の相続人が肩代わりを強いられる可能性があります。
相続税が支払えない ときの5つの対処方法
1. 延納
相続税を一括で納付することが難しい場合、延納という分割払いの制度を利用することが可能です。この方法では、5年から最長20年の期間で分割して納付することが認められます。ただし、延納期間中には利息にあたる利子税が課されるため、計画的な支払いが必要です。
参考:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm)
2. 物納
現金での納付が難しく、延納も選択できない場合には、物納という方法を利用できます。物納では、不動産などの財産そのものを相続税として納めます。ただし、物納での評価額は売却する場合よりも低くなる傾向があるため注意が必要です。
3. 相続放棄
相続税の支払いが難しい場合、相続放棄を検討することも一つの選択肢です。相続放棄を行うと、相続に関する権利と義務を全て放棄することができます。
相続放棄のメリット
相続放棄を行うことで、借金などのマイナスの財産も含めて相続しなくて済むため、相続税の支払いに悩む必要がなくなります。
相続放棄のデメリット
一度相続放棄を選択すると撤回ができないため、慎重な判断が必要です。また、プラスの財産も相続できなくなる点もデメリットといえます。
4. 親族や専門家への相談
相続税の支払いが難しい場合には、まず親族間で話し合いを行い、解決策を模索することが大切です。また、税理士や行政書士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスやサポートを受けられる可能性があります。
5. 事前の相続対策
相
続税の負担を軽減するためには、事前の相続対策が重要です。不動産の活用や贈与税を利用した資産移転など、適切な計画を立てることで、相続税の負担を軽減できます。
まとめ
相続税が支払えない場合には、多くのリスクやペナルティが伴います。しかし、延納や物納、相続放棄などの制度を活用することで、負担を軽減することが可能です。また、親族や専門家との相談を通じて、適切な対処方法を見つけることが重要です。事前の相続対策を講じることで、相続税の問題を未然に防ぐことができます。相続税について不安がある方は、ぜひ早めに専門家に相談しましょう。